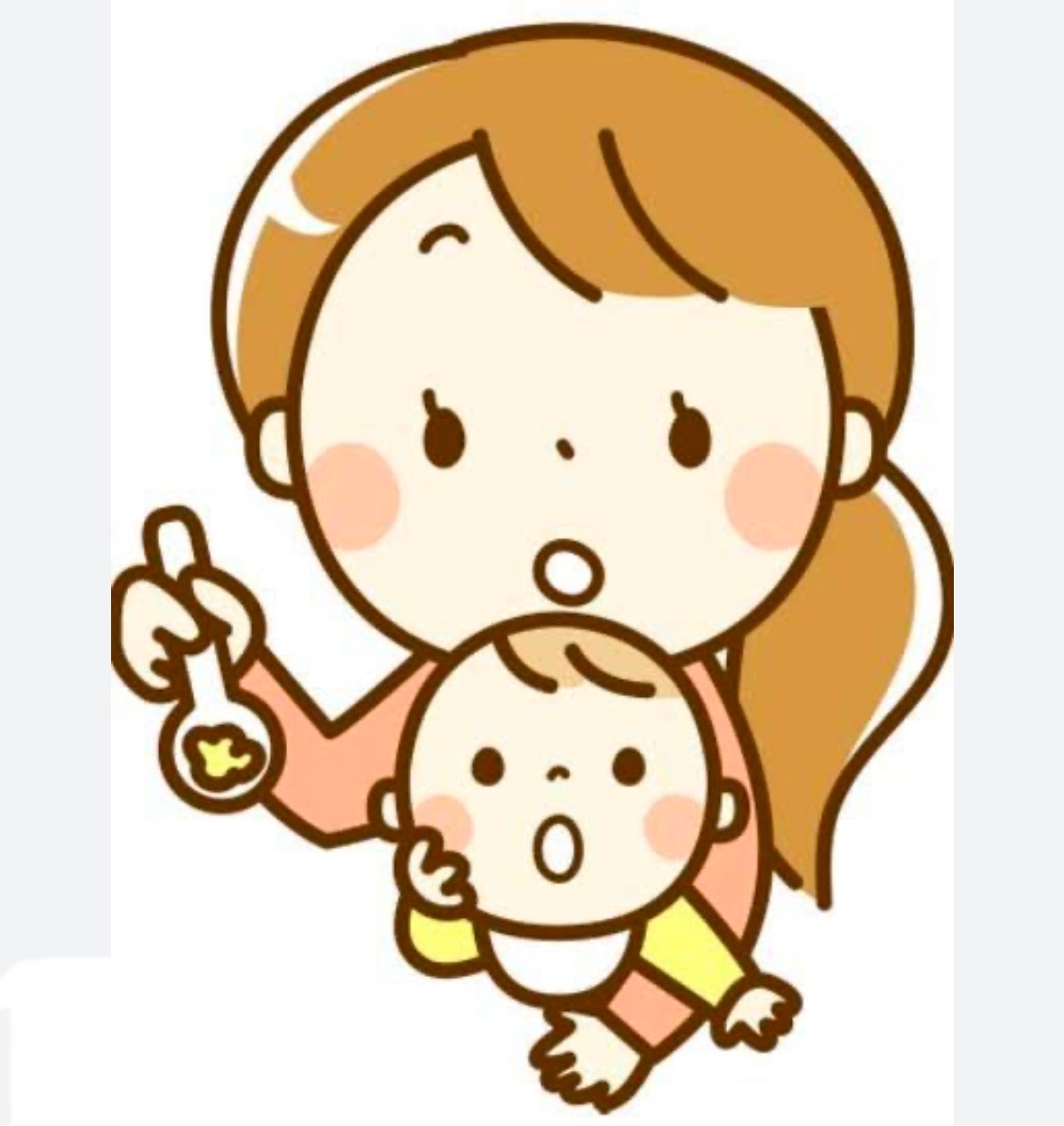要約
コロナが落ち着き、この1〜2年は0歳3ヶ月で入園されるお子様も増えてきました。 保育園での離乳食の進め方や粉ミルク提供について、小規模保育園での例となりますが、少しでも園でのイメージが出来ればいいなと思います。
○離乳食開始の目安
・生後5〜6ヶ月頃が一般的で、首が座り、スプーンを受け入れる準備が整った時期に始めます
・最初は10倍粥を小さじ1杯から始め、3日ごとに新しい食材を追加します。食材は舌で潰せる柔らかさに調整します
○月齢ごとの進め方
1、初期(5~6ヶ月)
・1日1回 飲み込む練習を目的に進めます ※母乳や粉ミルクが主な栄養源
・食物アレルギーに注意しながら、少量ずつ与えます
・家族にアレルギーがある場合は注意
2、中期(7~8ヶ月)
・食事回数を1日2回に増やし、ペースト状から少し形のある食材へ移行します
3、後期(9~11ヶ月)
・1日3回の食事リズムを確立。手づかみ食べやスプーン使用を促します
4、完了期(12~18ヶ月)
・大人の食事から取り分ける場合は薄味を心がけます。噛む練習ができる固さの食材も取り入れます

【注意点】
・アレルギー症状や体調変化(下痢・嘔吐など)に注意しながら進めます
・調味料は使わず、昆布だしなど素材の味を活かします
・保護者と連携し、家庭で試したことのある食材を園でも提供します
子どものペースに合わせた無理のない進行を大切にしています
○園:お子様に対しての取り組み
1、子どものペースを尊重
・子どもによって食欲や成長ペースが異なりますので月齢にこだわらず、無理なく進めます
・食事に興味を示さない場合は焦らない
2、食べる姿勢や環境を工夫
・椅子に座るのを嫌がる場合は膝の上で食べさせるなど、安心できる姿勢をとっています
・おもちゃは片付け、集中できる環境を整えます
3、食材や調理法の調節
・個々の発達状況に合わせて、食材の硬さや形状を調節します
┗家庭ではどのくらいの量を提供しているのか、固さや形状も確認します
・手づかみ食べが好きな子には持ちやすいスティック状にしたり、おにぎりに変更
4、食べる楽しさをを重視
・自分で食べたがる場合はスプーンや手づかみ食べを促し、食事の楽しみを育てます
┗テーブルも本人も、床もすごいことなります💦
・食べ物で遊んでも寛容に対応し、ポジティブな経験とします
┗落としたり、遊んでしまう量も加味し、多めの量を提供
5、写真で様子を掲示
なかなか言葉だけでは保護者の方に伝わらない事があるので、定期的に給食やおやつの様子、給食自体の写真を掲示します

最初は食べなくても、なかなか離乳食が進まなくても、いつの間にか食べれるようになります。
焦らずに本人のペースに合わせてすすめています
上記の事が柔軟に対応できるのは、小規模保育園の強みです💪
○園:離乳食の進め方
・保護者・保育士・調理師が協力して進めていきます
・食物アレルギーの懸念から、どんな食材でも必ず家庭で試したことのある食材を園で提供します
・当日の給食メニューの中で、摂取可能となった食材を使って離乳食を作りますので、可能な限り早めに色んな食材が食べれるようになっていた方が、提供される離乳食の食材も増える事になります
※離乳食を始める時期の目安は5〜6ヶ月ですが、最近は7ヶ月前後で始められるご家庭が多いです

○園:粉ミルクの提供について
・無料で提供(粉ミルクの銘柄が決まっている事が多いです)
┗入園前に確認し、味に慣れておくや、母乳のみの場合は哺乳瓶で粉ミルクを飲む練習をしておくと良いです。
・哺乳瓶の必要性の確認
┗基本、園の哺乳瓶を使用しますが、どうしても園で飲まない場合、ご家庭の飲み慣れた哺乳瓶をお借りする場合があります
・1歳の誕生月を目安に粉ミルク提供は終了を目安にしていますが、お子様の離乳食の進み具合により、延長する事もあります
・3ヶ月のお子様は1日3~4回(3時間おき)で提供し、離乳食の進み具合で回数や、飲む量を調節します
・粉ミルクを飲むタイミングは、個々のタイミングで提供しています
以上が小規模保育園での進め方、取り組みになります。
○保護者様は凄いです!
お仕事と子育ての両立をされている保護者様方はとっても凄いです✨✨
目安はあくまでも目安なので、焦らず保護者様のペースでご家庭での離乳食を進めて頂ければと思います😊
保育施設は、働く保護者の方々の支援も兼ねております。 保育士は子育てのプロフェッショナルです。安心してお預けし、頼ってください。保護者様もリフレッシュの時間は必要です🍀

少しでも参考になれば嬉しいです。
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。