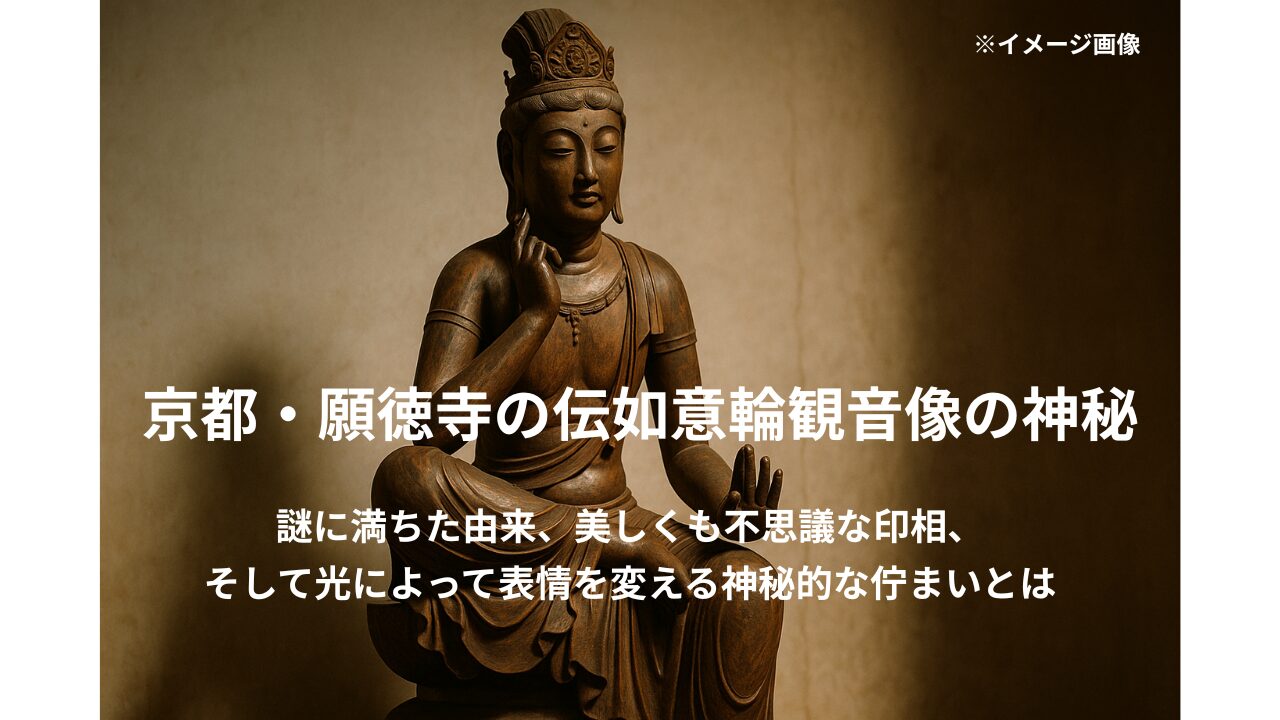【国宝】菩薩半跏像(伝如意輪観音)
平安時代前期(約1200年前)に造られた、国宝・木造菩薩半跏像(伝如意輪観音菩薩)。
高さは約88cm、カヤの一木造りで彩色はされておらず、静謐な佇まいが印象的です。
寺伝では如意輪観音と伝えられますが、通常の如意輪観音像は六臂(手が六本)であるのに対し手が二本(二臂)であることから虚空蔵菩薩などの別尊である可能性も指摘されています。
顔立ちや衣の表現などは中国唐代の様式の影響を受けていると考えられ、唐の国で作られたか、渡来人の手による制作との説もあります。
この像は半跏(片足を組む)で凛とした姿勢の美しい観音像で、宝菩提院 願徳寺のご本尊として尊ばれています。唐風の様式を取り入れた珍しい例として、日本の貴重な国宝仏像の一つであり、その由来や様式の詳細はまだ研究が続けられています。
不思議ポイント|独特な印相と構え
左手が施無畏印、右手が与願印という、通例とは逆の印相。
さらに、足の下げ具合も一般的な配置と反対です。
このような逆構成は非常に珍しく、像の神秘性を高めています。
作者と制作背景
- 作者は不明
- 平安時代前期(9〜10世紀頃)の制作
- 像の顔や衣の表現には唐風(中国唐代)の様式の影響が色濃く見られる
- 中国の唐で制作されたか、日本に渡来した渡来人(当時の中国や朝鮮半島からの仏師など)によって作られたという説が有力
- 寺伝では如意輪観音像とされていますが、二臂(手が二本)である点から虚空蔵菩薩や聖観音、月光菩薩という説も存在もあり、尊名や起源にはいまだ多くの謎が残されてる。
- カヤ材の一木造り、彩色なし
このように、作者や制作背景には多くの謎があり、唐風様式の影響と渡来文化の痕跡を持つ平安初期の重要な文化財である。
表情の変化が語る、仏像の魅力
この像は自然光と照明の差で表情が変わって見えることでも知られ、その美しさと謎めいた魅力によって多くの人々に尊ばれています。
- 照明下では凛とした表情に見える
- 自然光下では穏やかで優しい表情に
- 見る角度によって印象が変わる
具体的には、お堂の照明が当たっているときには凛々しく厳かな表情に見えますが、照明を消してお堂の入り口から入る自然光の下で見ると、より穏やかで優しい表情に変わるとのことです。この違いは、木造像の表面の微細な形状や陰影の見え方が変わることによるもので、光の角度や強さの違いが像の表情の印象に影響するためです。
その微妙な表情の変化が、この像の大きな魅力の一つとなっています。
多くの参拝者がこの表情の移ろいに心を打たれ、涙するほど感動を覚えるそうです。制作者が意図的にそうした効果を狙った可能性もあります。
「黒い艶」が生み出す独特の美
像がカヤの木の一木造りで彩色されていないことから、黒みを帯びた木肌の自然な質感が生かされていると考えられます。この黒い艶は、単なる黒色ではなく、木材の持つ深みと滑らかで光沢のある表面が、まるで黒い宝石のように輝く特徴的な美的要素です。
- 長い年月による自然な黒光り
- 彩色を施さず木の本来の色味や質感をそのまま活かしているため、漆のような滑らかで豊かな光沢がある。
- 木の油分による自然光沢
この艶やかさは像の品格を高め、見る角度や光によってさらなる表情の変化を見せてくれます。
展示の様子|奈良国立博物館「超国宝展」にて

2025年春、奈良国立博物館「超国宝―祈りのかがやき―」展にて展示されました。
- 真っ白な円形台座に単独で据え置かれたシンプルな展示空間
- 360度どこからでも鑑賞できる配置
- 衣文の精緻さや像のフォルムを存分に味わえる構成
この展示により、像のもつ凛々しさや美しさがさらに際立っていました。
(※衣文とは…美術用語として、着衣の襞の形や衣服のしわの様子を指します。)
実際にお会いして(筆者体験)
奈良国立博物館の特別展「超 国宝」で拝観致しました🙏✨
異国の風を感じる彫りの深いお顔立ちはとても整っていて、まっすぐ前を向いてこちらを見ているようでした。
流れるような衣文、黒く艶やかに光るふくよかな木肌──360°どの方向から見ても美しく、その存在感に圧倒されました。
そして、白い台座とのコントラストがその美しさを際立たせ、思わず見惚れてしまうほど。
背中の衣の間からのぞく素肌のリアルな造形もまた、美しくて忘れられません。
パンフレットにもこの御仏像のお写真が掲載されており、美しさがひと目で伝わってきます。(※掲載ができないのが残念です)
小さなお寺に秘められた大きな感動
宝菩提院 願徳寺は「京都一小さなお寺」とも称され、かつては地図にも載っていなかったほどですが、2006年の東京国立博物館での展示以降、多くの仏像ファンに知られる名作となりました。
ーー謎に満ちた由来、美しくも不思議な印相、そして光によって表情を変える神秘的な佇まいーー
この麗しく神々しい御仏に、お会いできて良かったです🙏✨
奈良国立博物館で出会ったこの菩薩半跏像(伝・如意輪観音)は、いまでも忘れられないほど深く私の心に残っています。
静かに微笑みをたたえるそのお姿に、ただただ見惚れてしまいました。
ひとり旅では、公共交通機関のアクセスの悪さがネックになることも。そんなときこそ、博物館での仏像鑑賞がおすすめです。本来はなかなか訪れにくい場所に安置されている仏像に、思いがけず出会えることもあるんです。
この仏像は、奈良県の「宝菩提院 願徳寺」に安置されており、現在は博物館での展示予定もなく、実物に会うにはお寺まで足を運ぶしかありません。
正直にお伝えすると、この寺院へは公共交通機関だけでのアクセスは難しく、私のブログのテーマからは外れてしまいます。それでもどうしても、この御仏像のことをお伝えしたかったのです。
もしかするといつか、また展示される機会があるかもしれません。そのときには、ぜひ多くの方に足を運んでほしい――そんな願いを込めて、この記事を書きました。
仏像との出会いは一期一会。
心に深く残る「とっておきの一体」にも、そっと目を向けていただけたら嬉しいです。
あわせて読みたい記事:このポーズを見て、ふと「あ、あの仏像にも似ているな」と思い出したのが、▶︎中宮寺の菩薩半跏思惟像です。こちらもぜひご覧ください。

▶️ 奈良国立博物館 公式サイトはこちら
そして仏像の中でも、今なお多くの人の心を惹きつける存在が
奈良・興福寺の阿修羅(あしゅら)像です。
▶ 阿修羅像の表情・造形・魅力を初心者にもわかりやすく解説した記事はこちら
拝観方法・アクセス
- 寺院名: 宝菩提院 願徳寺
- 天台宗の寺院
- 住所: 京都市西京区大原野南春日町1223-2
- 拝観料: 約400円
- アクセス:JR「東向日駅」または阪急「東向日駅」から阪急バス「南春日町」下車 徒歩25分
本堂は小さく静かな佇まい。住職の方による説明が受けられることもあり、貴重な仏像をゆったりと拝観できるそうです。
おわりに|仏像を通して心にふれる時間を
仏像の世界は、本当に、奥深くて、美しくて、人の心に静かに響くものだと思います。
そこには、言葉にしきれない感動や、目の前の仏像から伝わってくる優しさ、強さ、そして静けさがあります。
それを理解できる人は少ないかもしれないけれど、私が発信し続けることで、「なんかいいかも」って思ってくれる人が、きっと少しずつ増えていくーーー
仏像の魅力を、もっともっと、世の中に伝えていけますように🙏✨
そんな思いを込めて、このブログを書いています😊
🇺🇸 English Summary(英語要約)
The Seated Bodhisattva Statue at Hōbōdain Gantokuji: A Timeless Serenity
This article introduces the Seated Bodhisattva Statue, traditionally identified as Nyoirin Kannon, housed at Hōbōdain Gantokuji in Kyoto. A National Treasure of Japan, this wooden sculpture from the Heian period is renowned for its elegant half-lotus posture and deeply meditative expression. The statue’s downcast eyes and gentle smile embody a serene, compassionate presence that continues to inspire awe and tranquility in viewers today. The article also explores the temple’s peaceful location, accessible via public transportation, and the spiritual atmosphere surrounding this graceful figure of Buddhist art.