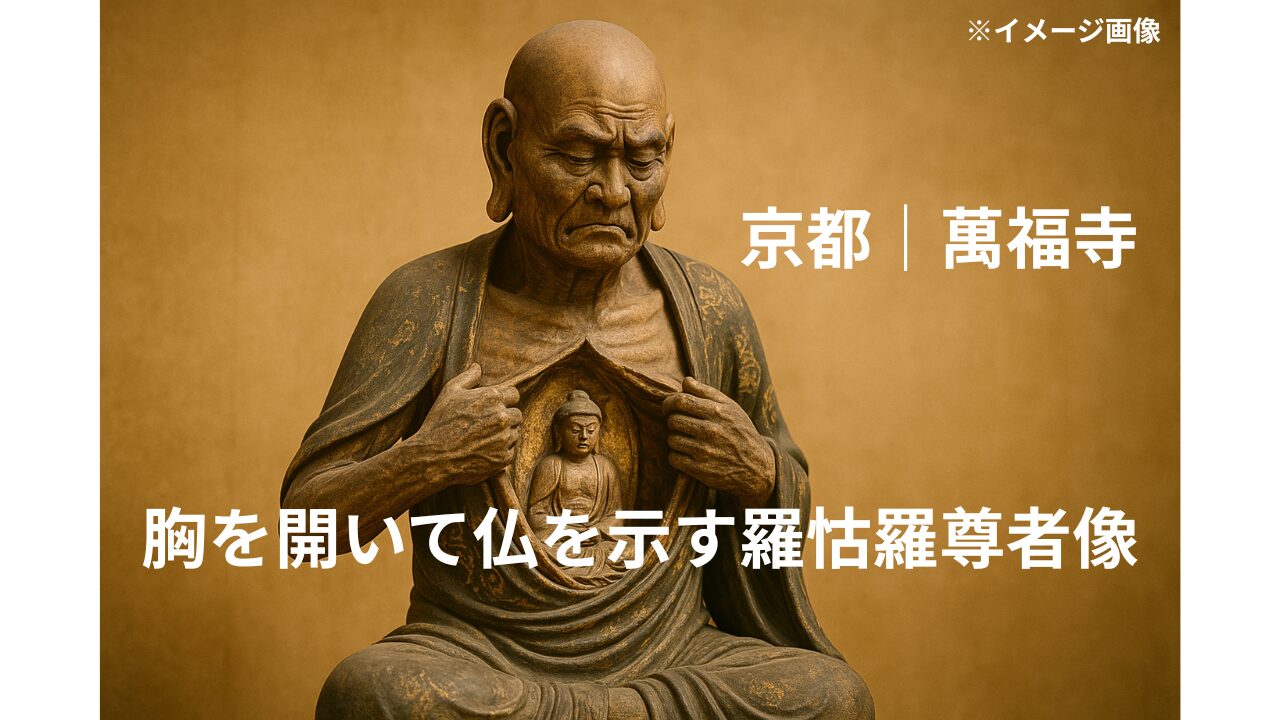一度見たら忘れられない仏像「羅怙羅尊者像(らごら そんじゃ ぞう)」
仏像好きの間ではよく知られている名作です。
私はこれまでに、
✔︎ 宇治の黄檗山(おうばくさん)萬福寺(まんぷくじ)
✔︎ 京都国立博物館の「日本・美のるつぼ」展
で、2度お会いしました。
初めて見たときの衝撃は強烈で、「え?どういうこと?」と足が止まりました。
しかし、羅怙羅尊者という人物の背景や、像に込められた意味を知ると、
この独特の表現にも深い理由があることがわかります。
この記事では、その魅力と鑑賞ポイントを
仏像初心者でも分かりやすく解説します。
京都をゆっくり巡りたい方へ。
仏像に会いに行く旅は、移動も含めて大切な時間です。
無理のない日程で、静かな余白を残した旅をおすすめします。
羅怙羅尊者像とは?|萬福寺に伝わる十八羅漢像のひとつ
羅怙羅尊者像は、
京都府 宇治市の黄檗山 萬福寺(おうばくさん まんぷくじ)に伝わる
「十八羅漢(じゅうはちらかん)」の1体です。
萬福寺は中国から伝わった黄檗宗のお寺で、
この像は 中国仏教美術の雰囲気を色濃く残す珍しい仏像 としても知られています。

造形の特徴|胸を開き、中に仏(釈迦)を見せる姿
最も大きな特徴は、
尊者が自分の胸(腹部)を両手で開き、その中にお釈迦さまの顔を見せていること。
文字だけ聞くと少し衝撃的に思えますが、
実際の像はとても品格があり、写実性と芸術性の高さに圧倒されます。
- 大きな耳環(じかん)
- 繊細な文様の彩色
- 水晶を使った瞳の表現
など、細部まで丁寧に作られており、
グロテスクさよりも神秘性の方が強く印象に残ります。
表現の意図|「心の中に仏がいる」という禅の教え
胸を開いて仏を見せる姿は、
「人は誰でも心の中に仏性(ぶっしょう)を持っている」
という仏教の核心を表したもの。
禅宗では、とくに “内側にある本質を見る” ことを重視します。
羅怙羅尊者像は、その思想をとても分かりやすく形にした、
象徴的な仏像です。
誰がつくったの?|中国から招かれた仏師・范道生(はんどうせい)
この像を制作したのは、明清時代の仏師・范道生(はんどうせい)。
- 時代:江戸時代前期(1664年)
- 来日目的:萬福寺の仏像制作のため
- 日本滞在:約1年
- 制作した仏像:約27体とも言われる
范道生の作品は、当時の日本仏像とは異なる迫力とリアリティがあり、
萬福寺の仏像群は日本美術史の中でも特に重要とされています。
技法と素材|中国伝統の「乾漆(かんしつ)造」
范道生は、**乾漆造(かんしつぞう)**という中国伝統の技法を用いて制作しました。
▷ 乾漆造とは?
- 木芯となる骨組みに布を貼り、
- その上から漆を何度も塗り重ねる
という、手間と技術が必要な方法。
日本では平安時代以降ほとんど使われなくなりましたが、
范道生によって再び息を吹き返した技法でもあります。
羅怙羅(らごら)とは?|釈迦の実子であり、修行者の一人
羅怙羅は、
お釈迦さまが王子だった時代に生まれた実の子ども です。
名前には「妨げ」「束縛」という意味がありますが、
それは父の出家時に生まれたため。
しかし実際は、父を慕い、幼い頃から修行に励んだとされ、
十八羅漢の一人として尊敬される人物 となりました。
像に感じられる「けなげさ」「心の奥にある想い」は、
この背景を知ることでより深まります。
十八羅漢像とは|悟りを開いた聖者たちの姿
萬福寺の大雄宝殿(だいおうほうでん)には、
18体の羅漢像がずらりと並んでいます。
- 体つきは力強く
- 表情も個性的
- 明清時代の中国仏教美術の様式を忠実に再現
日本の仏像ではなかなか見られない雰囲気で、
異国情緒に満ちた空間が広がります。
羅怙羅尊者像は、その中でも特に表現がユニークで人気が高い1体です。

鑑賞ポイント(初心者向け)
① 胸の中の「小さな釈迦」
心の中の仏性を表す、禅宗ならではの象徴表現。
② 顔の表情や水晶の瞳
生きているような目の輝きに注目です。
③ 彩色の美しさ
金泥や文様の細かさは、近くで見るほど圧巻。
④ 他の羅漢像との違い
萬福寺の十八羅漢は全体的に個性的。“並び”で見るとより深く味わえます。
まとめ|背景を知ると、もっと心に響く仏像
京都国立博物館の特別展でも、羅怙羅尊者像はフォトスポットとして人気でした。
胸を開いて内なる仏を示すという表現は衝撃的ですが、
「自分の中にこそ仏がいる」
という禅の教えを、とてもわかりやすく伝えてくれます。
釈迦の実子であり、名前に「妨げ」の意味を持ちながらも、
父のあとを追って修行の道を選んだ羅怙羅の人生を思うと、
そんな彼が「自分の胸の中に仏がいる」と示す姿は、
禅の本質を表しつつも、深い信心とけなげさが伝わってくるようです。
このような背景を知ると、羅怙羅尊者の思い、
そしてこの像が持つ “静かな強さ” をより深く感じられます。
羅怙羅尊者像は、奈良・宇治の萬福寺に安置されております🙏✨
ぜひ現地で見ていただきたいです。
京都市内での宿泊を検討する場合は、こちらも参考にしてみてください。
→京都エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)
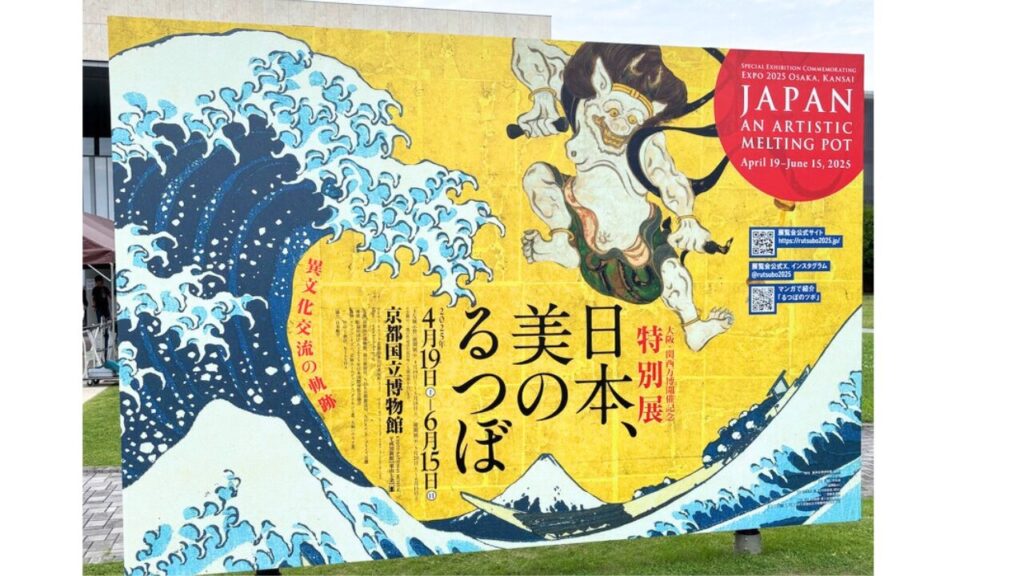
そして仏像の中でも、今なお多くの人の心を惹きつける存在が
奈良・興福寺の阿修羅(あしゅら)像です。
▶ 阿修羅像の表情・造形・魅力を初心者にもわかりやすく解説した記事はこちら
※本記事内の写真はすべて筆者が撮影したものです。
萬福寺の基本情報
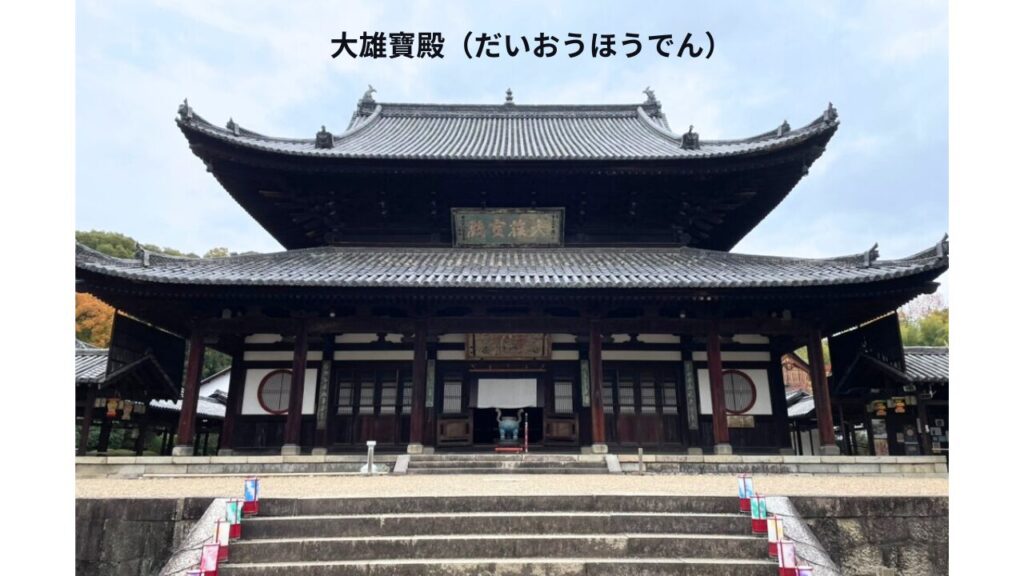
- 寺名:黄檗山 萬福寺(おうばくざん まんぷくじ)
- 住所:〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄三番割34
- 公式HP:https://www.obakusan.or.jp/
- 拝観情報:羅怙羅尊者像は「大雄宝殿」に安置されています。
→京都駅/烏丸駅周辺、早い、手軽、着崩れないで安心の着物レンタルなら夢館-ゆめやかた-

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。