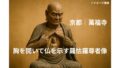はじめに

ご縁がありまして、3度お会いしております🙏✨
- 1度目:2021年10月 法隆寺の大宝蔵院にて
- 2度目:2025年5月 奈良 国立博物館「超 国宝」前期
- 3度目:2025年5月 奈良 国立博物館「超 国宝」後期
「超 国宝」展(奈良国立博物館)での展示方法が素晴らしかったです!
鮮やかな水色の土台の上に鎮座している
「百済観音像(くだらかんのんぞう)」は
”天に向かって立ち上がる永遠の灯”そのものに見えました。
📍「百済観音像(くだらかんのんぞう)」
奈良県斑鳩町・法隆寺の大宝蔵院に安置されている
飛鳥時代(7世紀中頃)の木造観音菩薩立像で、
日本を代表する国宝のひとつです。
厳粛な雰囲気が多い飛鳥時代の仏像の中で、
柔和で親しみやすい表情や、しなやかに伸びる指先、
流れるような天衣(てんね)が特徴的です。
小さな目や口元のアルカイックスマイルも多くの人に愛されています
主な特徴
- 像高:209〜211cmの長身、八頭身のしなやかなプロポーション
- 材質:クスノキの一材から彫り出された一木造
- 表情:小さな目と口、やわらかな微笑み(アルカイックスマイル)
- ポーズ:左手に水瓶、右手は手のひらを上に向けて人々に救いの手を差し伸べる姿勢
- 光背:華麗な光背(後光)が像の優美さを引き立てる
歴史と由来
百済から伝わったという伝承もありますが、
実際には日本国内で造像されたと考えられています。
法隆寺での初出は17世紀で、それ以前の所在や由来には謎が多く残されています。
飛鳥仏の中で異彩を放つ理由
- プロポーションと造形美:腰高で八頭身という非常にスリムな体型と、
直線と曲線が絶妙に調和した優美なシルエットを持っています。
まるで宙に浮いているかのような軽やかさや、横から見ても美しい天衣のカーブなど、
従来の飛鳥仏には見られない造形表現が特徴 - やわらかく親しみやすい表情:多くの飛鳥仏が厳粛で神秘的な雰囲気を持つのに対し、
百済観音像は小さな目と口、控えめな微笑み(アルカイックスマイル)による
やさしい表情が印象的です。
見る人に親しみや温もりを感じさせる点も、他の飛鳥仏と大きく異なる。 - 写実性と立体感:止利式仏像(釈迦三尊像など)は正面観照性が強く、
立体感に乏しいのが特徴ですが、
百済観音像は側面から見ても優雅なフォルムを持ち、
より自然な人体表現を追求しています。
これは飛鳥時代の仏像の中でも進化した技法と言えます。 - 人間味のある造形:無表情や筋骨隆々な表現が多い他の仏像に比べ、
百済観音像は「自然な人間」を忠実に表現し、
今にも語りかけてきそうな人間味と身近さを醸し出している。
これらの点から、
百済観音像は従来の飛鳥仏とは一線を画す存在として、
飛鳥仏の中で異彩を放つと高く評価されています。
伝来や起源に謎が多い歴史的背景
- 記録の欠如:百済観音像に関する最古の記録は、
1698年(元禄11年)の『法隆寺諸堂仏躰数量記』で
「虚空蔵菩薩立像(こくうぞうぼさつりつぞう)」として登場しますが、
それ以前の文献や記録が一切存在しません。
そのため、造像当初から法隆寺にあったのか、
後世に他寺から移されたのかも定かではありません。 - 伝来経路の不明確さ:伝承や一部記録では
「百済国から渡来した天竺(インド)製の像」とされていますが、
実際には材質が国産のクスノキであることや、
造形技法から日本国内で制作されたと考えられています。
また、橘寺や中宮寺から移されたという説もありますが、
いずれも確証はありません。 - 名称の由来:「百済観音」という名称が定着したのは大正時代以降で、
それ以前は「虚空蔵菩薩立像(こくうぞうぼさつりつぞう)」と呼ばれていました。
(「虚空蔵立像」:正式な名称は「木造 虚空蔵菩薩立像」) - 仏教伝来との関係:百済観音像は、百済から日本に伝わった
仏教文化の象徴とされますが、実際の像の制作地や時期、作者などは不明です。
百済が日本へ仏教を伝える重要な役割を果たしたことから、
像にもその名が付けられたと考えられます。
このように、百済観音像は制作年代や伝来経路、旧所在、作者、法隆寺との関係など、多くの点で史料的な裏付けがなく、歴史的背景に謎が多い仏像とされています。
仏教文化に与えた影響
- 日本木彫仏の新様式の提示
- 異文化交流の象徴
- 芸術・文学・精神文化へのインスピレーション
- 仏像鑑賞意識の深化
日本仏教美術の発展、異文化交流の象徴、精神文化への影響、
美術鑑賞意識の深化など、多方面にわたり
仏教文化へ大きな影響を与えたと考えられます。
法隆寺で見られる代表的な御仏像

◎救世観音像(夢殿、秘仏):夢殿の本尊で、聖徳太子の等身像とも伝わる秘仏です。
◎釈迦三尊像(しゃかさんぞんぞう)(止利仏師作):金堂の本尊で、
飛鳥時代(623年)に止利仏師によって造られた日本を代表する仏像です。
中央に釈迦如来、その両脇に薬王菩薩・薬上菩薩が配置され、
アーモンド型の目や「アルカイックスマイル」と呼ばれる微笑みが特徴です。
◎薬師如来像(平安時代):金堂の東の間や大講堂に安置されている
薬師如来像も有名で、平安時代の優美な作風が見られます。
◎阿弥陀三尊像(鎌倉時代):金堂西の間に安置され、
鎌倉時代の仏像として知られています。
◎五重塔 塑像群(涅槃像土):五重塔の初層には、
釈迦の生涯の4場面を粘土で表現した塑像群があり、
特に「涅槃像土」は「法隆寺の泣き仏」として有名です。
このほかにも、四天王像や夢違観音像など、
各時代を代表する仏像が多数安置されています。
法隆寺は日本仏像史を語るうえで欠かせない名宝の宝庫です。
「超 国宝」展での展示方法(奈良国立博物館)
- ガラスなし・360度から鑑賞可能:法隆寺ではガラスケース越しに見上げる形ですが、
超国宝展ではガラスケースに入れず、目線のやや上程度の高さに安置。
像の前後左右、360度から細部までじっくり観察できます。 - 後ろ姿や細部の観察が可能:普段は見られない背中や光背の取り付け構造、
竹を模した支柱の意匠、天衣の流れなども間近で確認できます。
特に光背の支柱が竹の意匠であることや、
宝冠の石が実は紺碧のガラス玉であることなど、
通常の拝観では気づきにくい細部も注目ポイントです。 - 水色の土台が仏の清らかさを象徴:仏像の蓮華座は、蓮の花が泥水の中から
清らかに咲く様子を象徴しており、仏が「煩悩の世界」にありながらも
清らかであることを示します。
土台の水色は「泥沼の水面」や「水そのもの」を表現している。 - 特別なライティング:展示会独自のライティングで、像の曲線美や質感、
装飾の美しさがより際立つように演出されています。 - 展示会場の導線:展示室に入ると最初に百済観音像が現れる構成で、
その存在感と美しさを印象的に体験できます。
このように、超国宝展では百済観音像を360度、ガラス越しでなく、
細部までじっくり観察できる特別な展示方法が採用されており、
来場者にとって極めて貴重な鑑賞体験となっていました。
仏像好きにとって、たまらなくありがたい演出でした🙏✨

▶︎ 仏像の展示方法によって印象が大きく変わることについては、
こちらの記事でも詳しく紹介しています。
合わせてご覧いただければ、鑑賞の奥深さがより伝わるかと思います。
▶︎ 奈良国立博物館 公式サイトはこちら
補足情報
法隆寺の大宝蔵院にて拝観可能。特別展では海外にも出展実績あり。
通常の安置ではガラス越しですが、超国宝展では間近で360度観察できました!
アルカイックスマイル(古典的微笑)
「百済観音像」と同様に、中宮寺の「菩薩半跏像」も
穏やかな微笑みが美しい仏像です。
法隆寺からも近いので、ぜひ立ち寄ってみてください。
※アルカイックスマイル(archaic smile)とは、
主に古代ギリシャのアルカイック時代の彫刻や、
日本の飛鳥時代の仏像などに見られる、
感情を抑えた表情の中で口元だけがわずかに微笑んでいるように
表現された特徴的な微笑みのことです
そして仏像の中でも、今なお多くの人の心を惹きつける存在が
奈良・興福寺の阿修羅(あしゅら)像です。
▶ 阿修羅像の表情・造形・魅力を初心者にもわかりやすく解説した記事はこちら
まとめ
唯一無二の独特なお姿と謎めいた歴史に魅力を感じました。
「超 国宝」展の展示方法で、百済観音像の美しさを最大限に体験できました。
これからも仏像旅を続け、新たな感動を求めていきたいと思います。
京都・奈良観光や仏像巡りを計画中の方へ
仏像に会いに行く旅は、移動も含めて大切な時間です。
無理のない日程で、静かな余白を残した旅をおすすめします。
宿泊も検討している方は、こちらから最新の宿泊情報をご覧いただけます。
→京都エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)
→奈良エリアの宿泊先を探す(楽天トラベル)
法隆寺の基本情報

宗派:聖徳宗 総本山
所在地:〒636-0115 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1
公式サイト:https://www.horyuji.or.jp/
\百済観音像は、法隆寺内の大宝蔵院にて参拝することができます/
最新情報は、公式HPにてご確認ください

合わせて読みたい記事
・微笑む仏像として知られる中宮寺の菩薩半跏思惟像を詳しく書いた記事はこちら
▶︎奈良・中宮寺「菩薩半跏像」|穏やかな微笑みと気品のある美しさ
・法隆寺 釈迦三尊像|飛鳥時代の傑作と鑑賞ポイント
【アクセス・見どころ】を詳しく書いた記事はこちら
▶︎法隆寺で出会う釈迦三尊像|飛鳥の祈りと美の原点
※本記事内の写真はすべて筆者が撮影したものです。
おわりに|仏像を通して心にふれる時間を
仏像の世界は、本当に、奥深くて、美しくて、人の心に静かに響くものだと思います。
そこには、言葉にしきれない感動や、目の前の仏像から伝わってくる優しさ、強さ、そして静けさがあります。
それを理解できる人は少ないかもしれないけれど、私が発信し続けることで、「なんかいいかも」って思ってくれる人が、きっと少しずつ増えていくーーー
仏像の魅力を、もっともっと、世の中に伝えていけますように🙏✨
そんな思いを込めて、このブログを書いています😊
🇺🇸 English Summary (英語要約)
Kudara Kannon Statue at Hōryū-ji, Nara
The Kudara Kannon is a wooden standing statue of the Bodhisattva Kannon (Avalokiteshvara), enshrined at the Great Treasure Hall of Hōryū-ji Temple in Nara, Japan. Dating back to the mid-7th century (Asuka period), it is considered one of Japan’s national treasures and a masterpiece of early Japanese Buddhist sculpture.
The statue stands at over 2 meters tall, showcasing a graceful, slender eight-head proportion carved from a single piece of camphor wood. It features a gentle “Archaic Smile”, subtle facial expression, and a peaceful pose with one hand offering salvation and the other holding a water vessel. The refined details of the garment and elegant silhouette set it apart from other Buddhist statues of the same era.
Despite its name, “Kudara” (referring to the ancient Korean kingdom of Baekje), the statue was likely made in Japan, possibly by an immigrant Baekje craftsman. Its origin, transmission, and early location remain a mystery, with the first historical mention appearing only in the 17th century.
The statue is notable for breaking away from the flat, frontal style typical of early Asuka sculptures, instead offering a more realistic, three-dimensional, and humanistic representation. It has deeply influenced the evolution of Japanese Buddhist art and has been a subject of admiration among writers and scholars, including Tetsurō Watsuji.
The author shares personal experiences of viewing the statue three times—once at Hōryū-ji and twice at the 2025 “Super National Treasures” Exhibition at the Nara National Museum, where the piece was displayed without glass, under special lighting, and viewable from 360 degrees. This rare exhibition allowed for intimate appreciation of fine details, including the bamboo-inspired halo support and blue glass gems on the crown.
Finally, the article situates the Kudara Kannon within the broader Buddhist art context of Hōryū-ji, introducing other iconic statues and highlighting the spiritual serenity and cultural symbolism of its gentle smile—similar to the “Bodhisattva Half-Lotus Thinking Statue” at nearby Chūgū-ji Temple.
※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。